 助手
助手博士〜、『Take On Me なぜ人気』ってよく検索されてるんですけど、この曲ってなんでそんなに長年愛されてるんですか?



いい質問ね!『Take On Me』は1985年にa-haがリリースした名曲で、シンセのリフと高音ボーカルがとても印象的なの。さらに、アニメと実写を組み合わせたミュージックビデオも当時は革新的で、MTV全盛期に強烈なインパクトを残したのよ。



へぇ〜!最近でもSNSでカバーやミームが流行ってるの見ました!昔の曲なのに、今の若い世代にもウケてるのってすごいですよね。



そうなの。歌詞の切なさや制作の裏話も含めて、いろんな面から心に響くからこそ、世代を超えて支持されてるのよ。この記事では、音楽・映像・文化の3つの視点からその魅力を詳しく紹介していくから、ぜひ最後まで読んでみてね!
なぜ「Take on me」はこれほどまでに世界中で愛され続けているのでしょうか。a-haが生んだこの楽曲は、印象的なシンセサウンドと高音ボーカル、そしてアニメと実写を融合させた革新的なMVで注目を集めました。歌詞の意味や再録音のエピソード、ミームやカバー文化まで、多面的な魅力が詰まった名曲です。この記事では、Take on me がなぜ人気なのか、その理由を映像・音楽・文化の視点から解説します。
- ミュージックビデオの革新性と映像技術の影響
- シンセポップとしての音楽的魅力とサウンドの特徴
- チャート成績やメディアでの活用による知名度の広がり
- 歌詞や制作背景に込められた深いストーリー性
Take on meはなぜ人気?映像と音の革新が理由
- 世界を驚かせたミュージックビデオの衝撃
- 鉛筆スケッチと現実を融合させた演出
- ノルウェー発シンセポップの魅力
- サビの高音域が耳に残るボーカル力
- 時代の空気を掴んだ80年代の象徴
世界を驚かせたミュージックビデオの衝撃
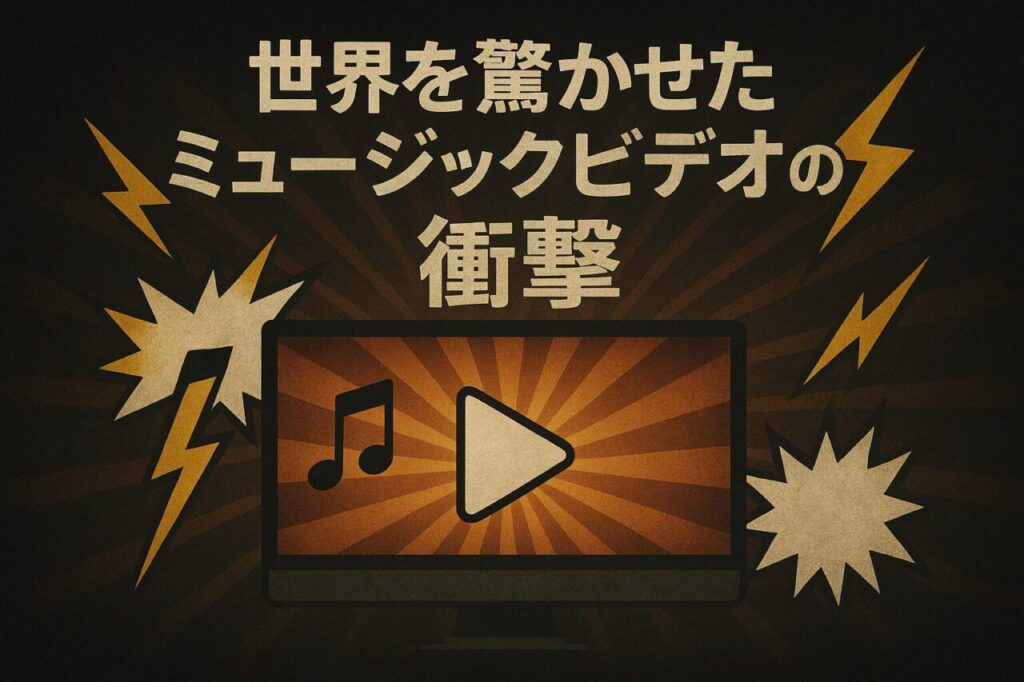
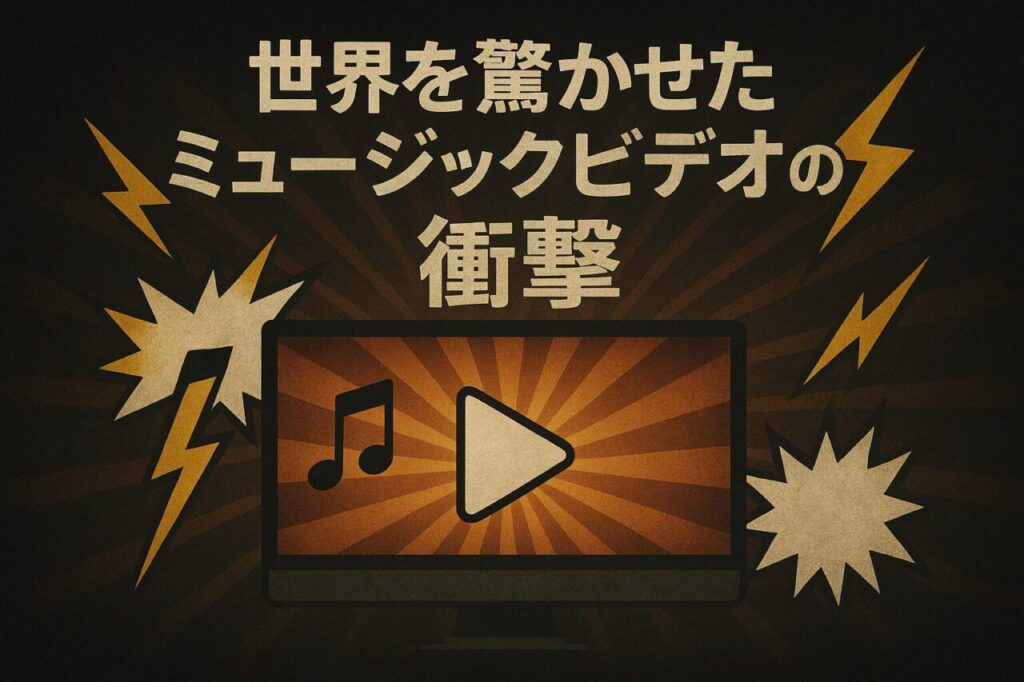
1985年にリリースされたa-haの「Take On Me」は、音楽だけでなく、その映像作品としての革新性によっても世界的な評価を得ました。特に注目されたのが、実写映像と手描きアニメーションを融合させた独創的なミュージックビデオです。
実写とアニメが融合した伝説のミュージックビデオ
- 使用された技法は「ロトスコープ」。実写映像を一コマずつトレースし、アニメーションに変換する非常に手間のかかる表現方法
- 登場人物が紙の上を動くように描かれ、現実と漫画が交錯する幻想的な世界観が展開される
- ストーリーは、ヒロインが読んでいるコミックから主人公(モートン・ハルケット)が飛び出す場面から始まる
- ヒロインも漫画の中へ引き込まれ、アニメと実写が交錯するドラマチックな展開に
- 楽曲の切なさと非現実的な映像表現が調和し、強い印象を残す構成に仕上がっている
- MTVでの反響は大きく、若者を中心に人気が爆発
- MTVミュージックビデオ・アワードで6部門を受賞し、映像と音楽が一体となる時代の象徴となった
「Take On Me」は、ポップソングとしての魅力だけでなく、ビジュアルアートとしての完成度の高さでも注目され、以降のMV制作のスタイルにも大きな影響を与えることになります。



現代でもYouTubeやSNSで再注目され続けているのは、こうした映像と音楽が一体となった表現力の強さゆえと言えるわ。
鉛筆スケッチと現実を融合させた演出
「Take On Me」のミュージックビデオにおける最大の技術的革新は、ロトスコープというアニメーション手法の本格的な活用にありました。これは、実写映像を元に、一コマ一コマを手描きでトレースしていくという非常に緻密で労力のかかる技法です。動きの滑らかさとリアルさを兼ね備えながら、まるで鉛筆で描いたような質感のアニメーションを生み出すことができます。
現実と空想を行き来する映像体験と物語構造
- 疾走感のあるサウンドと、柔らかく高揚感あるボーカルが映像と調和し、強烈な印象を残す作品に仕上がっている
- 当時のミュージックビデオでは珍しかったロトスコープ技術を用い、音楽と映像の融合を実現
- 実写の俳優がスケッチ風のアニメ世界に入り込み、最後には現実に戻る構成で幻想的な映像体験を演出
- 物語の軸は「恋愛」と「選択」。現実世界のヒロインに、コミックの中から主人公が手を差し伸べ、異世界へ誘う展開
- 視聴者自身も、まるでページの中へ引き込まれるような没入感を味わえる
- 非現実的なビジュアルでありながら、描かれる感情は人間的でリアルな恋心を感じさせる
- 映像表現は、楽曲が持つ儚さや一瞬の決断というテーマを補完
結果として、このミュージックビデオは「見る音楽」という概念を定着させる転機となり、視覚的にも聴覚的にも記憶に残る作品として、音楽史に大きな足跡を残しました。



映像と音が互いに補完し合いながら、感情の奥深さを描き出すことに成功した、まさに完成度の高いアートといえるでしょう。
ノルウェー発シンセポップの魅力


a-haの「Take On Me」が音楽的に放つ最大の魅力は、軽快で耳に残るシンセサウンドにあります。イントロから印象的に響くフレーズは、ローランド社のアナログシンセサイザー「JUNO-60」によって生み出されたもので、この楽器特有の太く温かみのある音色が、曲全体のアイデンティティを形作っています。電子音でありながらも有機的で、どこか人間味を感じさせるこの音は、1980年代のシンセポップサウンドの象徴として、多くのミュージシャンやリスナーに影響を与えました。
北欧らしさと技術が光る「Take On Me」のサウンドの魅力
- バンドとしての演奏力やアレンジ能力の高さが発揮され、打ち込み中心のバンドという印象を超える存在感を示した
- 「Take On Me」のサウンドは明るくポップでありながら、北欧アーティストならではの繊細さや透明感も持ち合わせている
- アップテンポな曲調の中に、コード進行やメロディに漂う物悲しさがあり、聴く人の感情に静かに寄り添う情緒がある
- この独特のバランスが、曲を一過性のヒットで終わらせず、世代を超えて愛される理由のひとつとなっている
- ボーカルのモートン・ハルケットは広い音域を持ち、高音のサビを軽やかに歌い上げる表現力が特徴
- そのハイトーンボイスがシンセサウンドと絡み合い、楽曲全体に浮遊感と伸びやかさを与えている
- 当時のライブ環境ではシンセ主体の音の再現が難しく、スタジオと同じクオリティを再現するには課題があった
- a-haはその課題に対し、楽器のバランスや構成を工夫することで、ライブ向けのアレンジを確立
加えて、ノルウェー出身ということも、当時の音楽シーンでは新鮮な驚きをもって受け止められました。当時のポップ市場はイギリスやアメリカ中心だったため、北欧から登場した国際的バンドとして、a-haはまさに新しい波を起こす存在でした。



彼らのサウンドは“北欧ポップ”という概念を世界に広めるきっかけともなり、現在まで続くスカンジナビアン・ポップスの流れの原点として位置づけられているわ。
サビの高音域が耳に残るボーカル力
a-haのボーカリストであるモートン・ハルケットの歌声は、”Take On Me”の印象を決定づける重要な要素の一つです。特にサビ部分の高音域は、聴く人の記憶に強く残り、この曲を唯一無二の存在にしています。
モートン・ハルケットの圧倒的な声域と歌唱力
- 実際にa-haの初期のツアーでは、体調管理や声のコンディション維持が大きな課題となっていた
- モートンの声域は約3オクターブとされ、ポップミュージック界でも非常に広い部類に入る
- 通常のポップスではあまり聴けないような高音を、自然で滑らかに歌い上げることができる
- 高音域の響きが楽曲のエモーショナルな部分を際立たせ、リスナーの感情に強く訴えかける要因となっている
- 特に「Take On Me」のサビに登場する “I’ll be gone in a day or two” の一節は、突き抜けるような高音で印象的
- このフレーズは技術的にも非常に難易度が高く、正確に再現できるアーティストは限られている
- それだけに、モートンの歌唱力と音域の広さが際立ち、他のアーティストとの差別化にもつながっている
- 一方で、高音域を多用するスタイルはライブでの安定性や喉への負担といった課題もある
とはいえ、サビの高音が持つインパクトは、曲全体のイメージを決定づける強力な武器であり、今なお多くのリスナーにとっての魅力となっています。
時代の空気を掴んだ80年代の象徴


“Take On Me”は、そのサウンドや映像表現だけでなく、80年代という時代の雰囲気を体現した象徴的な存在でもあります。この曲には、当時のテクノロジー、ファッション、エンタメ文化など、あらゆる要素が凝縮されています。
時代を象徴したサウンドと映像、そして再評価の波
- 「Take On Me」も、レトロ感と新鮮さを併せ持つ楽曲として、再び脚光を浴びる存在となっている
- 1980年代はMTVの登場により、音楽が映像と結びついて広がった時代
- a-haはインパクトあるミュージックビデオとキャッチーなサウンドを融合させ、若者文化の中心に躍り出た
- 「Take On Me」には、肩パッド入りのジャケット、軽やかなシンセサウンド、未来感とノスタルジーが共存する雰囲気など、当時の要素が詰め込まれている
- 1985年のリリース当時は、アナログからデジタルへの過渡期であり、シンセサイザーやドラムマシンを取り入れたサウンドは時代の最先端として注目された
- このスタイルは90年代に一度下火になったが、2000年代以降の80年代リバイバルによって再評価が進んだ
このように、”Take On Me”は単なる一曲にとどまらず、時代そのものの「空気感」を封じ込めた音楽として、今も多くの人々に愛され続けているのです。
Take on meはなぜ人気?時代を超えて愛される理由
- 歴史的ヒットを記録したチャート実績
- 映画やCMで繰り返される引用の多さ
- 異色の誕生秘話と再録音の物語
- 実は奥深い歌詞に込められた想い
- 現代でもバズるミームとカバー文化
- YouTubeで今なお伸び続ける再生数
歴史的ヒットを記録したチャート実績
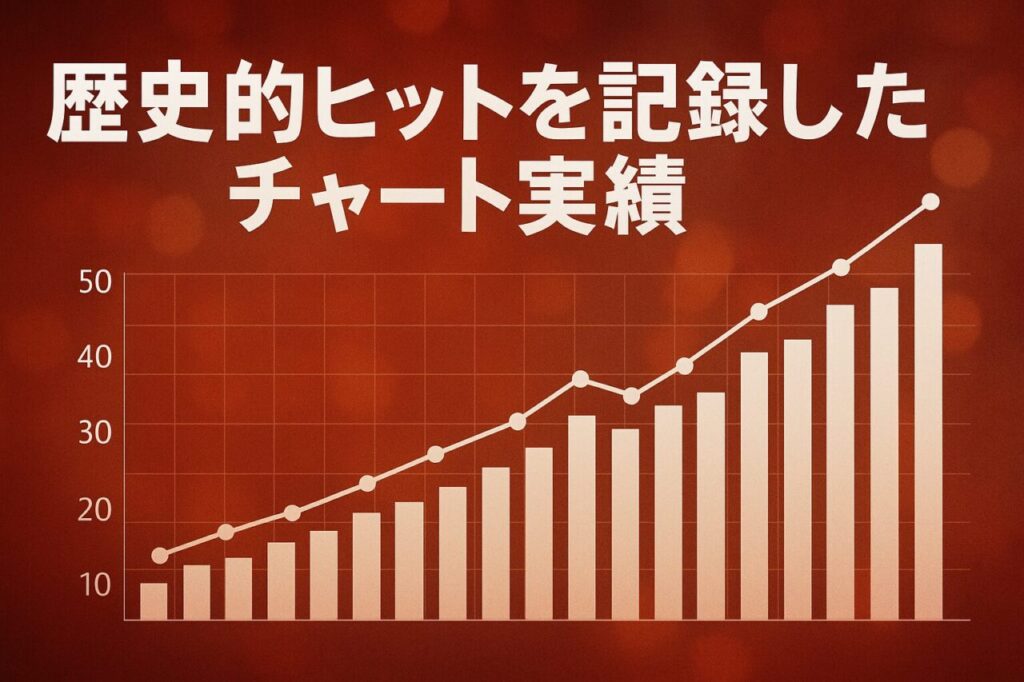
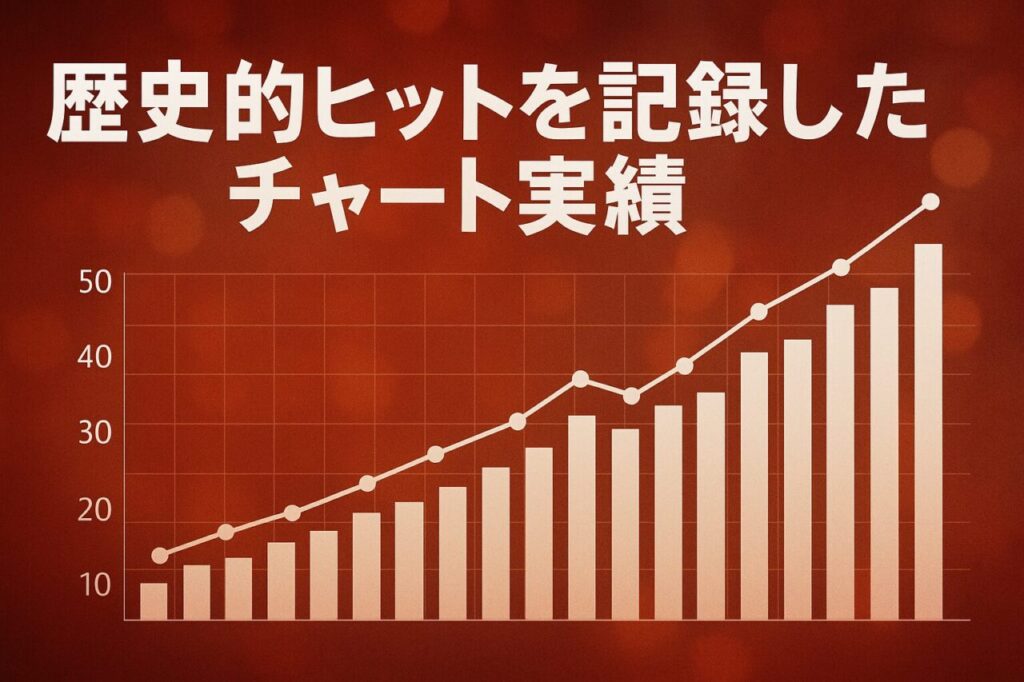
“Take On Me”は、1985年のリリース直後から世界中で爆発的なヒットを記録しました。特にアメリカのBillboard Hot 100では1位を獲得し、これがノルウェー出身のバンドとしては史上初の快挙となりました。
この曲はアメリカのみならず、イギリス、カナダ、オーストラリア、ドイツなど複数の国のシングルチャートでも上位にランクインしています。最終的には12カ国で1位を獲得し、世界的な成功を収めました。日本でも洋楽ファンを中心に根強い人気があり、バンドはFNS歌謡祭にも出演し、その名を広く知られるようになりました。
加えて、当時のMTVでのヘビーローテーションが後押しとなり、視聴者の間で話題が拡大。売上としてはシングルとアルバムを合わせて5000万枚以上を記録しています。
このように、”Take On Me”は音楽チャートにおいても記録的な成果を残した一曲であり、a-haにとっても世界的ブレイクのきっかけとなる重要な作品でした。
映画やCMで繰り返される引用の多さ
“Take On Me”は、そのリリースから数十年を経た今でも、映画やCMなどのさまざまなメディアで繰り返し引用されています。その使用頻度の高さは、楽曲の持つ普遍性と親しみやすさの証とも言えます。
メディアで再評価される「Take On Me」の多様な使われ方
- CMでは企業イメージを明るくポジティブに印象づけるBGMとして選ばれ、日本のセブンイレブンでもインストゥルメンタルが使用される例がある
- 映画『ラ・ラ・ランド』では、ジャズ好きの主人公が嫌々80年代ポップを演奏する場面で使用され、音楽ジャンル間の対比として機能
- 『デッドプール2』ではアコースティックバージョンが感動的なシーンで流れ、原曲とは異なる静かな魅力を引き出している
- アニメ映画『怪盗グルーのミニオン大脱走』や『バンブルビー』では、80年代のノスタルジーを象徴する楽曲として採用
- いずれの作品でも、映像と音楽が組み合わさることで強い印象を残す演出に貢献
こうした幅広いメディア露出によって、”Take On Me”はさまざまな世代に知られ続けており、結果として再生数やダウンロード数の増加にもつながっています。
異色の誕生秘話と再録音の物語
“Take On Me”の誕生には、通常のヒット曲にはない複雑な背景があります。この曲は完成までに3年以上の歳月がかかっており、その間に何度も再編曲と再録音が繰り返されました。
誕生までの歩みを時系列で整理
世界的ヒットとなったa-haの「Take On Me」は、実は何度も録音・再構築を経て完成した楽曲です。以下に、その制作過程を時系列でまとめました。
| 時期・段階 | 出来事 | 内容・ポイント |
|---|---|---|
| 初期構想 | Bridges時代 | マグネが15歳でシンセリフを発案 |
| メンバー加入 | モートン加入 | バンドの方向性が固まる |
| 1回目の録音 | プロデュース:トニー・マンスフィールド | 音が無機質で商業的に不発 |
| 2回目の録音 | プロデュース:アラン・ターニー | 現在の形に近づく |
| 3回目のリリース | MV制作:スティーブ・バロン | 革新的映像が話題となり世界的ヒットに |
さらに2017年には、MTV Unplugged企画でアコースティックバージョンが披露され、静かな感情表現とともに楽曲の新たな一面が評価されました。こうして、曲は時代とともに進化しながら、その本質を失うことなく受け継がれ続けています。
実は奥深い歌詞に込められた想い
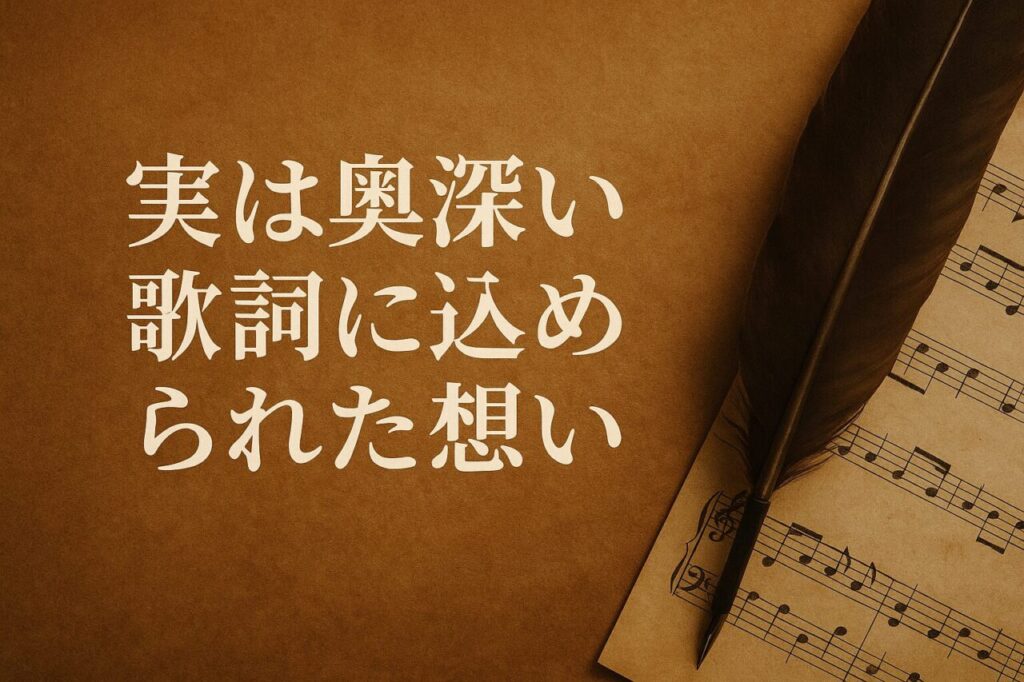
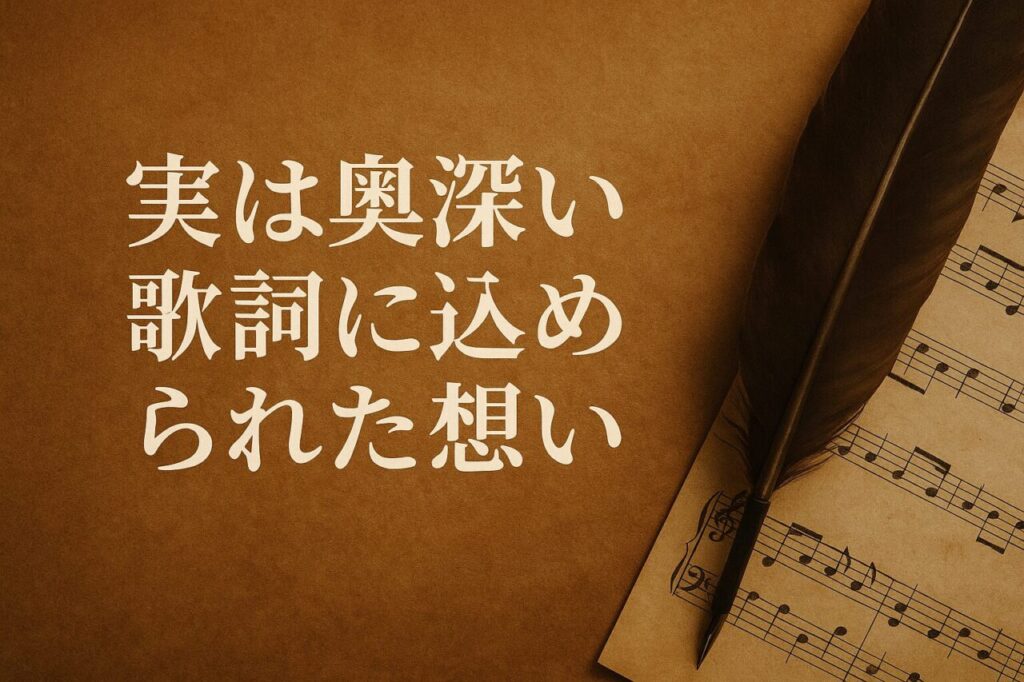
“Take On Me”の魅力はサウンドや映像にとどまらず、歌詞にも深い意味が込められています。一見するとシンプルでキャッチーなラブソングのように思えますが、読み解いていくと「距離感」や「すれ違い」、「一瞬の決意」といった、普遍的な人間関係のテーマが浮かび上がってきます。
冒頭の “We’re talking away / I don’t know what / I’m to say I’ll say it anyway” というフレーズは、気持ちをうまく言葉にできないもどかしさを表現しています。恋愛における曖昧さや不安、でも相手に近づきたいという願いを、ストレートながら繊細な表現で描いています。
さらに “I’ll be gone in a day or two” という歌詞には、時間の儚さや決断の必要性が込められています。「今、この瞬間に動かないと、もう遅いかもしれない」という切実さが伝わってくる一節です。このように、曲全体を通して“すれ違うふたりの想い”や“曖昧な関係性の中で揺れる心”が描かれており、聴く人の状況によって様々な解釈が可能です。
恋愛だけでなく、仕事や人生の選択といった場面にも通じる普遍的な感情が含まれているため、何度聴いても共感や気づきを得られる楽曲といえるでしょう。
現代でもバズるミームとカバー文化
“Take On Me”はリリースから40年近く経った今も、インターネット上で繰り返しバズを起こしています。その中心となっているのが、ミームとしての活用と、さまざまなアーティストによるカバーです。
現代でも愛され続ける理由とその広がり
a-haの名曲「Take On Me」は、今もなおSNSや映像作品、カバーなど多彩な形で再評価されています。以下に、その活用例と評価を表にまとめました。
| 活用ジャンル | 内容の詳細 | 影響・評価 |
|---|---|---|
| SNS・動画サイト | MVのシーンやシンセリフを使ったパロディ、リミックス | ユーモラスな演出で若年層にも浸透、新たなファンを獲得 |
| 映像表現 | アニメと実写が交差する演出をクリエイターが再構築 | 映像作品や創作のインスピレーションとして再利用される |
| カバー音源 | ウィーザーのカバー、アコースティック版、EDM風アレンジ、子ども向けアニメ等 | 国・世代・ジャンルを超えて多様に再生産される |
| 受容と課題 | ネタ化や過剰露出による“飽き”の指摘も | 一方でメロディと感情の強さはあらゆる形でも評価され続ける |
このように、”Take On Me”は時代やメディアを超えて、多様なかたちで人々の記憶と文化に根付いているのです。
YouTubeで今なお伸び続ける再生数


YouTube上で公開されている”Take On Me”の公式ミュージックビデオは、14億回以上の再生回数を記録しています。1980年代にリリースされた楽曲としては異例の数字であり、時代を超えて世界中で愛され続けている証拠と言えるでしょう。
再生数が伸び続ける理由
- 人気の拡散がさらに注目を生むという好循環が生まれている
- ミュージックビデオの映像演出が独自性に富み、初見でも強烈な印象を残す
- シンセサイザーのリフとハイトーンボーカルが時代感を持ちながらも新鮮に響く
- 若い世代にも刺さるサウンドで、世代を超えて受け入れられている
- 映画・アニメ・CMなどの起用をきっかけに再視聴される機会が多い
- 『デッドプール2』でのアコースティック版など、異なる形での魅力再発見が話題に
- 高い再生数自体が「なぜ人気なのか」という興味を引き、新たな検索・再生を呼ぶ
今後もコラボやリバイバルが行われるたびに、新たな再生の波が生まれる可能性が高く、”Take On Me”は永遠のヒットソングとしての地位を保ち続けるでしょう。
Take on meがなぜ今も人気なのかを紐解く
今回のポイントを以下にまとめました。
- アニメと実写を融合した革新的なミュージックビデオが注目を集めた
- ロトスコープ技法により手描きの温かみある映像を実現した
- 現実とフィクションを行き来するストーリー構成が印象深い
- MTVアワードで6冠を獲得し映像作品としても評価された
- シンセサイザーを主軸とした爽やかで哀愁あるサウンドが特徴
- 北欧特有の透明感ある空気感を音で表現した点が新鮮だった
- ボーカルの高音域が美しくサビが耳に残りやすい
- 3オクターブを超える歌唱力が唯一無二の存在感を放つ
- 当時のMTV文化と時代背景に完璧にマッチしていた
- 世界12カ国でチャート1位を獲得するなど実績も申し分ない
- 数々の映画やCMで引用され続け、定番曲として定着した
- 3度のリリースと再録音を経た執念のヒット曲である
- 歌詞に込められた切なさと一瞬の決意が共感を呼ぶ
- インターネットミームとして現代でも幅広く認知されている
- YouTubeで14億回再生され続ける持続的な人気がある